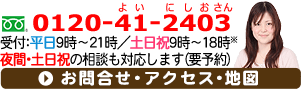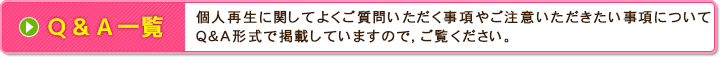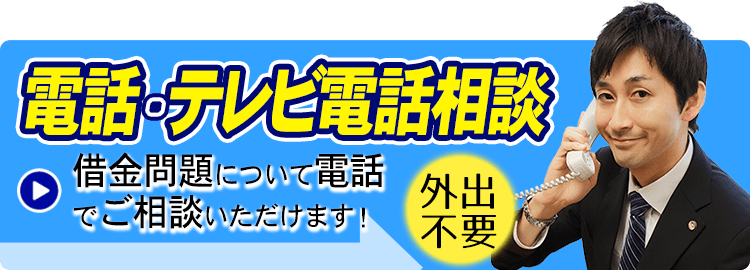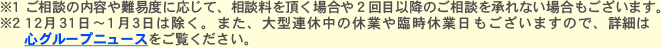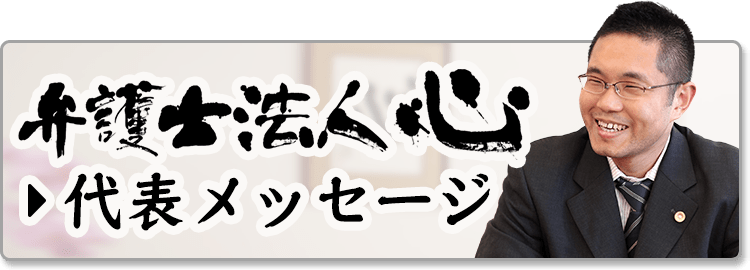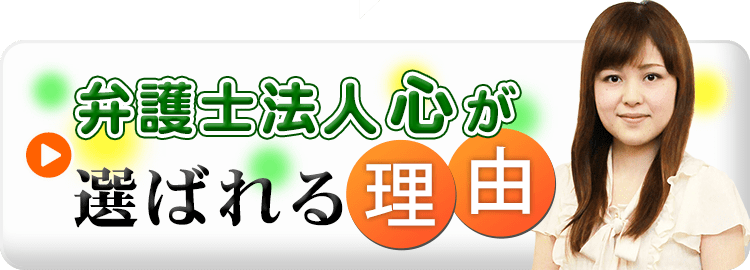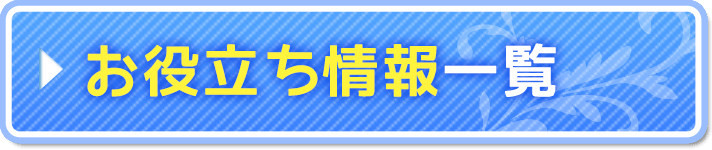お役立ち情報
個人再生をすると財産は没収されるのか
1 個人再生では基本的に財産は失いません
個人再生は、自己破産とは異なり、保有財産を処分せずに債務を減額できる可能性がある手続きです。
原則として、担保権が設定されている財産でなければ、失うことはありません。
住宅ローンや自動車ローンが残っていて、自宅不動産や自動車など担保権が設定されている財産があったとしても、一定の条件を満たすことで失わずに済むことがあります。
実務においては、特に住宅ローンが残っている自宅を残したいという思いから、個人再生を選ぶ人も多いと考えられます。
住宅ローン特則(住宅資金特別条項)の利用が可能なケースであれば、住宅ローン以外の債務を減額しつつ、住宅ローンの支払いは続けることで自宅を守ることができます。
なお、個人再生には小規模個人再生と給与所得者再生の2つがありますが、本稿では実務上用いられることが多い小規模個人再生を前提に説明します。
2 財産の価値次第では個人再生後の返済額が高くなることがある
ただし、個人再生は保有財産を維持できる一方で、その財産の評価額が個人再生後の返済金額に影響を与える点には注意が必要です。
個人再生には、債権者保護の観点から、債務者の方の保有財産の評価額(清算価値)以上の金額を返済しなければならないというルール(清算価値保障原則)が存在します。
例えば、債務総額が300万円であり、本来100万円まで減額できる場合であっても、保有財産の評価額が150万円であると、返済額は150万円以上になります。
評価対象となる財産の代表的なものとしては、一定金額を超える現金や預貯金、有価証券、不動産(抵当権が設定されている場合は査定額から残債務額を控除した金額)、自動車、解約返戻金のある保険、退職金見込額の一部などが挙げられます。
財産を失うことはないものの、保有財産の価値が高いと個人再生後の返済額が大きくなることは理解しておく必要があります。
3 担保権が設定されている財産は失うことがある
1において、担保権が設定されている財産でも残せる可能性がある旨を説明しました。
もっとも、自宅に設定された抵当権の実行を回避できる住宅資金特別条項や、自宅以外の担保権の実行を回避できる別除権協定の適用を受けるためには、厳格な要件を満たす必要があります。
担保権が設定されている財産をお持ちの場合には、法的な判断、見込みを踏まえ、事前に十分な検討をすることをおすすめします。
住宅資金特別条項を利用できない場合 個人再生後にクレジットカードは作れるのか